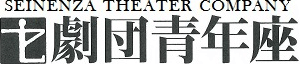- トップ
- 青年座について
青年座について(日本語)
ご挨拶
2022年。コロナ禍は収まりそうになるとまた変異種で勢いを増す。未だ先が見えない。
2月24日ロシアはウクライナに軍事侵攻。4万人以上の死者、5万人以上の負傷者、1360万人の避難民を出しこちらも先が見えない。そんな中カタールでワールドカップが開催された。日本の健闘が光った。しかし世界の状況が様々な形で影を落とす。スポーツ、演劇。ともに平和でなければ成立しない。そしてこの文化を守るためにも演劇を発信し続けなければならない。2022年も多くの芝居を上演した。年明け1月は『横濱短篇ホテル』の四国、神奈川、東北の旅と紀伊國屋ホールでの最終公演。全195回上演。新作はシライケイタ作、金澤菜乃英演出『ある王妃の死』で始まった。朝鮮国王・高宗の王妃が暗殺された前代未聞の事件を描いた。5・6月。中島淳彦作、黒岩亮演出『夫婦レコード』。2004年初演の舞台の再演。中島淳彦氏への追悼公演。続いて新劇交流プロジェクトとして宮本研作、鵜山仁演出『美しきものの伝説』。新劇団7劇団による合同公演。6月、10月、津嘉山正種がひとり語りを行う。『沖縄の魂~瀬長亀次郎物語』『戦世を語る』。今年は『命口節』沖縄公演も予定している。8月。井上光晴原作、小松幹生脚色、鈴木完一郎演出、山本龍二演出補『明日』は関越、近畿を巡演。途中コロナ陽性者が多数出た為公演中止となるも、11月に振替公演を行い完走。9・10月、青年座初登場ピンク地底人3号作、宮田慶子演出『燐光のイルカたち』。刺激的な舞台となった。
そして2023年1月。土田英生作、金澤菜乃英演出『時をちぎれ』。13年ぶり3度目の土田ワールド。3月。2021年初演、岩瀬晶子作、須藤黄英演出『シェアの法則』が早々と全国に旅立つ。5月。水上勉作、『金閣炎上』。1982年初演の舞台が宮田慶子演出で蘇る。7月。本公演初の韓国戯曲。イ・ヤング作、石川樹里翻訳、須藤黄英演出『黄色い封筒』。2014年、実際に起きた労働争議にセウォル号事件が重なる。10月、2017年『旗を高く掲げよ』で青年座初登場の古川健新作『同盟通信』。演出は黒岩亮。
2019年新春号で「青年座劇場及び青年座の建替えについてのご報告」をさせていただいた。当初の予定ではすでに新らしい建物ができているはずだが、未だ進展はない。今少し静観頂ければ幸いです。
青年座創立69年目。本年もよろしくお願い申し上げます。
青年座の活動
1994年の創立四拾周年以降はマキノノゾミ(『横濱短篇ホテル』他)、永井愛(『見よ、飛行機の高く飛べるを』他)、鈴木聡(『をんな善哉』他)、最近では長田育恵(『砂塵のニケ』)、シライケイタ(『安楽病棟』)、瀬戸山美咲(『残り火』)、中村ノブアキ(『DNA』)、松田正隆(『東京ストーリー』)、松本哲也(『ありがとサンキュー!』)、岩瀬晶子(『シェアの法則』)と現代演劇を代表する劇作家の新作を次々と上演、また『明日-1945年8月8日・長崎-』(井上光晴原作、小松幹生脚色)、『ブルーストッキングの女たち』(宮本研作)など繰り返し上演すべき作品を組み込み、重層的な公演活動を行っています。
また2012年からはポリー・ステナム作『THAT FACE~その顔』、マイク・バートレット作『LOVE, LOVE, LOVE』など、海外の現代戯曲にも積極的に取り組み、2019年上演の『SWEAT スウェット』(リン・ノッテージ作)では高い評価をいただきました。
東京での本公演の他、全国の市民劇場・演劇鑑賞会でのロングラン公演、新劇交流プロジェクト公演(『その人を知らず』)など、劇団の枠を超えた交流など多彩な演劇活動を展開しています。
一方、現代演劇の未来を担う俳優・スタッフの養成を目的とし、1975年より青年座研究所(2年制)をスタートさせ多くの人材を輩出してきました。2021年も本科・実習科で多くの研究生が学びます。
さらに青年座映画放送株式会社を通し、所属俳優・スタッフの舞台・テレビ・ラジオ・映画出演、演出のマネージメントを行い、日本の現代演劇・エンターテイメントの発展に大きく貢献しています。
受賞
| 1968年 | 第23回芸術祭奨励賞(『禿の女歌手』の成果に対して) |
|---|---|
| 1968年 | 第3回紀伊國屋演劇賞団体賞(年間の公演活動に対して) |
| 1971年 | 第6回紀伊國屋演劇賞団体賞(年間の公演活動に対して) |
| 1973年 | 第28回芸術祭優秀賞(『三文オペラ』の成果に対して) |
| 1979年 | 東京都優秀児童演劇選定優秀賞(『ブンナよ、木からおりてこい』) |
| 1979年 | 厚生省児童福祉文化賞(『ブンナよ、木からおりてこい』) |
| 1980年 | 第34回芸術祭優秀賞(『ブンナよ、木からおりてこい』) |
| 1981年 | 第35回芸術祭大賞(「五人の作家による連続公演の企画・制作」) |
| 1985年 | 東京都優秀児童演劇選定優秀賞(『ブンナよ、木からおりてこい』) 厚生省児童福祉文化賞(『ブンナよ、木からおりてこい』) |
| 1987年 | 第42回芸術祭芸術祭賞(『国境のある家」の成果に対して) |
| 1990年 | 平成元年度芸術祭芸術祭賞(『盟三五大切」の成果に対して) |
| 1997年 | 第31回紀伊國屋演劇賞団体賞 (『三文オペラ』『審判』『ベクター』などの舞台成果に対して) |
| 1998年 | 第5回読売演劇賞優秀作品賞(『フユヒコ』の舞台成果に対して) |
| 1998年 | 第52回芸術祭大賞(『見よ、飛行機の高く飛べるを』の成果に対して) |
青年座について(English)
History
Founded in 1954. On December 17, 1954, the company staged its first performance, Daisan no Shogen (The Third Testimony) by Rinzo Shiina, at the Haiyuza Theater.The program contains the following, opening statement: The membership of Seinenza is comprised of youths. Our primary aim is to produce new and innovative plays. In this way, we at Seinenza hope to anchor and express Japan's ever-changing reality in theater. Within Japan's living and moving society, we seek to transform into theatre the very air that touches our skin... Founding members Masahiko Naruse, Sojiro Amano, Hiroshi Hijikata, Bin Moritsuka, Yoshihiro Nakadai, Kotoe Hatsui, Hisano Yamaoka, Shinko Ujiie, Emiko Azuma, Hiroko Seki.
Awards
| 1968 | 23rd Art Festival Prize of Recognition (for Hage no Onna Kashu [The Bald Female Singer]) |
|---|---|
| 1968 | 3rd kinokuniya Group Theatre Prize (in recognition of annual production activities) |
| 1971 | 6th Kinokuniya Group Theatre Prize (in recognition of annual production activities) |
| 1973 | 28th Art Festival Prize of Excellence (for Sanmon Opera[Three Penny Opera]) |
| 1979 | Tokyo Metropolitan Outstanding Children's Theatre Choice of Excellence Award (for Boonah, Come Down) |
| 1979 | Welfare Ministry's Children's Welfare Cultural Award (for Boonah,Come Down) |
| 1980 | 34th Art Festival Award of Excellence (for Boonah, Come Down) |
| 1981 | 35th Art Festival Grand Prize (In recognition of the collaborative programming and production by 5 playwrights) |
| 1990 | Art Festival Art Festival Award of the 1st Year of Heisei (for Kamikaketesanngotaisetsu) |
| 1997 | 31st Kinokuniya Group Theatre Award (for Three Penny Opera, Shinpan Boonah, Come Down and Vector) |
| 1998 | 5th Yomiuri Theatre Prize Award of Excellent Work (for Fuyuhiko) |
| 1998 | 52nd Art Festival Grand Prize (for Miyo, Hikoki no Takaku Toberuwo [Look, How High the Airplane Flies]) |
劇団概要
| 劇団名 | 有限会社 劇団青年座 |
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-53-12 |
| TEL | 03-5478-8571 |
| 代表取締役 | 濵田正敏(森正敏) |
| 取締役 | 宮田慶子 紫雲幸一 横堀悦夫 青木鉄仁 綱島郷太郎 |
| 監査役 | 新庄和彦 |
| 劇団員 | 俳優 160名 スタッフ 48名 2020年1月1日現在 |